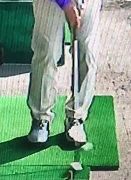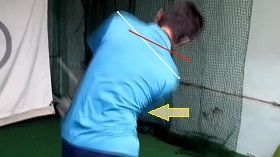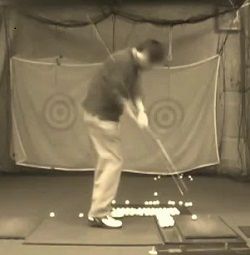- テーマ:
- ブログ
L型ブリストルパターに限りませんが、
より良いパッティングをするのには
以下の点のご注意下さい。
①深くかがんで ボールに被るように構えない
× 〇


これには幾つか理由があります。
 振り子のクラブを使うので
振り子のクラブを使うのでロフト変化、ヘッドの高さ変化が激しく
安定した距離感が生み出しにくくなります。
 ヘッドのある場所と 自分のヘッド(頭)が
ヘッドのある場所と 自分のヘッド(頭)がいつも反対に動くので
スイングボトム・パッティングストロークボトムが
アドレスよりも右にズレます。
が、故に 長い距離でのダフリ であったり
距離によって度合いは変わりますが、
常時 上がり行程でのインパクトの為、
薄いトップ気味の球になり易いです。
 トップショットは ショットの中で一番回転数が増えます。
トップショットは ショットの中で一番回転数が増えます。通常のパッティングでは 回転数は 300~800回転
1000回転以下のことが殆どですが、
トップになると 打つ距離とあまり関係なく
4000~5000回転なんて言うのもザラ・・・。
その分 エネルギーは食われ ボールは飛びません。
 何も感じなければ良いですが、
何も感じなければ良いですが、お家で、とか、パッティングの練習をそこそこする のであれば
このかがみ方、前屈は 腰を痛める原因になります。
……私の年齢で 5分やれば もうしんどいです。




 コースで 緊張感を生み出し易い ので
コースで 緊張感を生み出し易い ので避けた方が良いと思います。
 この構えでは 距離感を生み出す、タッチの違いを生み出すのが
この構えでは 距離感を生み出す、タッチの違いを生み出すのが首回りや背中の筋肉です。
前傾して それでなくとも重い自分の体を支えるのに
かなり使用している その筋肉が距離感の元 なのですから
微妙な距離感は生み出しにくい と思います。
②腕さばき 肘さばきで打ってしまいましょう。
肩を使う ショルダーストロークは
肩であれば、結局 腕
背中であれば 繊細な調整に不向き という あいまいな箇所が
距離感を作るコトになります。
故に ひじの曲げ伸ばしで
〇右腕の肘の使い方や
〇左腕の動かし方 で 距離感を造りましょう。
 カギになるのは
カギになるのは右ひじの伸ばしと左手首(もしくは左ひじの逃げ)の関係です。


ひじを伸ばし 右手が押すのは シャフトやクラブではなく
クラブを持った左手、左手首を押すような感じ になります。
よって 右ひじの伸び と 左手首の平側への折れ(左ひじの逃げ)
がつながった関係になります。
ヘッドの高さを大きく変えず
フェースがずっと ボールを追いかけるような
そんな感じになります。
このパッティングストロークは
そのまま ショットとつながっていきます。
両肩の揺さぶりでストロークする その感じは
スイングにとっては 手打ち です。
からだの回転 ではなく
体のひねり になってしまいますので
出来れば パッティングで
回転を体のひねり 肩のひねり と結びつけない方が良いと思います。

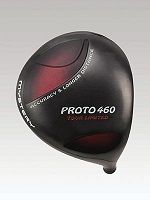
 そこ ご注意を。
そこ ご注意を。