ゴルフクラブの真理を追いかけ、重たいヘッド&柔らかなシャフトを通して ゴルフを考え スウィングを考えるヘン〇ツ親爺 誰よりも振らず 誰よりも飛ばす ボールをつぶせ をモットーに! 〒238-0024 神奈川県横須賀市大矢部3-14-10 ◆電話 046-804-1480 ◆ファックス 046-804-2442 ◆メールアドレス hummingbirdsports@jcom.home.ne.jp
2020年8月25日火曜日
両手離し(スプリットハンド)ドリルを経て【激変しました】
☞ハミングバードスポルテ本店
http://blog.livedoor.jp/hbs/
☞ハミングバード YouTube
https://www.youtube.com/user/HummingBirdSports?feature=mhee
☞ハミングバードFB
https://www.facebook.com/sporte.hummingbird
☞ハミングバードHP
http://www.hummingbird-sports.com/
2020年8月24日月曜日
はじめてのアドレス『スタンス』
☞ハミングバードスポルテ本店
http://blog.livedoor.jp/hbs/
まず 知っている人には無用ですが、
ゴルフのスタンス、スタンスの向きは
目標方向、ターゲット に 平行に
電車の線路のように どこまでも交わらず、平行です。

自分のスタンスを 目標、
例えば ドライバーで言うとフェアウェイの目標点や
グリーン上のピンであったり 目標に向けてはいけません。
ボールと当たるヘッドは 自分のスタンスと平行
というのが 基準になりますので
それでは ヘッド~ボールは目標よりも右を向いてしまいます。
打つ距離などによっても異なりますが、
アイアンでグリーンをセンターを狙う場合など
自分のからだやスタンスは グリーンの左端であったり、
場合によっては グリーンの左外を向いてる場合もあります。
次にスタンス、
ボールの飛ばしたい方向を決める スタンス
足、というか 靴の向き ですが、
この基準になるのは 両足のかかと です。
多くの人が 右打ちの場合
左足、左靴 の方を多めに開き、
右足、右靴 の方が少なめです。
この状況の中で つま先がターゲットに向いていると
本当のスタンスは右を向いていることになり
希望の目標方向にボールを飛ばすには
「ひっかけ」を覚えなくてはならなくなります。
また 薄く右を向いていると
感覚的においている ボールの位置が中(右)に
感じてしまうので、前(左)に置きがちです。
これに グリップ・・・左グリップのガブリと深く握りしめてしまう
状態が絡むと 肩は㊧ スタンスは㊨ がより強くなります。
スタンスはボールの左右に対する置き位置と密接に関係があるので
グリップによって肩は㊧ スタンスの基準をつま先、スタンスは㊨
によって ボールの置き位置があやふやになり易く
それはミスショットの誘発します。
 正直 コースでのショットのミス要因の多くはコレ だと思います。
正直 コースでのショットのミス要因の多くはコレ だと思います。
まず 知っている人には無用ですが、
ゴルフのスタンス、スタンスの向きは
目標方向、ターゲット に 平行に
電車の線路のように どこまでも交わらず、平行です。

自分のスタンスを 目標、
例えば ドライバーで言うとフェアウェイの目標点や
グリーン上のピンであったり 目標に向けてはいけません。
ボールと当たるヘッドは 自分のスタンスと平行
というのが 基準になりますので
それでは ヘッド~ボールは目標よりも右を向いてしまいます。
打つ距離などによっても異なりますが、
アイアンでグリーンをセンターを狙う場合など
自分のからだやスタンスは グリーンの左端であったり、
場合によっては グリーンの左外を向いてる場合もあります。
次にスタンス、
ボールの飛ばしたい方向を決める スタンス
足、というか 靴の向き ですが、
この基準になるのは 両足のかかと です。
多くの人が 右打ちの場合
左足、左靴 の方を多めに開き、
右足、右靴 の方が少なめです。
この状況の中で つま先がターゲットに向いていると
本当のスタンスは右を向いていることになり
希望の目標方向にボールを飛ばすには
「ひっかけ」を覚えなくてはならなくなります。
また 薄く右を向いていると
感覚的においている ボールの位置が中(右)に
感じてしまうので、前(左)に置きがちです。
これに グリップ・・・左グリップのガブリと深く握りしめてしまう
状態が絡むと 肩は㊧ スタンスは㊨ がより強くなります。
スタンスはボールの左右に対する置き位置と密接に関係があるので
グリップによって肩は㊧ スタンスの基準をつま先、スタンスは㊨
によって ボールの置き位置があやふやになり易く
それはミスショットの誘発します。
 正直 コースでのショットのミス要因の多くはコレ だと思います。
正直 コースでのショットのミス要因の多くはコレ だと思います。
2020年8月23日日曜日
フェースローテーションをしないゴルフスイング
☞ハミングバードスポルテ本店
http://blog.livedoor.jp/hbs/
☞ハミングバード YouTube
https://www.youtube.com/user/HummingBirdSports?feature=mhee
☞ハミングバードFB
https://www.facebook.com/sporte.hummingbird
☞ハミングバードHP
http://www.hummingbird-sports.com/
(投稿)達人リートレビノ式
☞ハミングバードスポルテ本店
http://blog.livedoor.jp/hbs/
早速、練習場で『達人リートレビノ式』試して参りました。
不安に感じたのは始めの数球で
(店主)お手紙ありがとうございます。
一般的には
◯インパクトは ボールと正対して…とか
◯体を開くコト
◯アウトサイドインになるコト
◯ボールをよく見るコト
◯左サイドの壁
など 気が付かないうちに
インパクトで左サイドを止めるコトの『暗示』
をかけられているのかも知れません。
【達人リートレビノ式 インパクトはココだよ!】は
フルショット、ドライバーなどにも勿論ですが、
特に アプローチの距離感には特効薬と成り得ます。
仰る通り、からだを止めて 手で振るスイングは
管理できない 放り投げるようなヘッド で打つのですから
ヘッドスピードの管理が出来ません。
 動作とヘッドスピードに関係性が薄い です。
動作とヘッドスピードに関係性が薄い です。
からだの回転で打てるようになると
自分の運動速度が そのままヘッドスピードになり、
ロフトやフェースの向きの変化 だけでなく
ヘッドの上下動も少なくなりますから
自分のモノにすれば 効果は絶大と思います。
ゴルフを始められた方に
この「達人リートレビノ式」を教えれば
終生、アプローチやショットに深く苦しまないで済む と
思うのですがね~。 冗談ですが、業界の陰謀かも…。
早速、練習場で『達人リートレビノ式』試して参りました。
左サイドを止めずに振り切ると
いままで 体(きっと左サイドですね)を止め
その分、手で下に振っていたことがよく判ります。
(キャスティングというか、自分的にはフェースローテーション)
(キャスティングというか、自分的にはフェースローテーション)
よくよく考えてみると
ボールに正対した状態から左向きの行為は
フェースターンと全く同じ意図、方向性なんですよね。
始めは下に振らないので届かないかと思いきや、
今までより遥かにダフリやトップも少なく、クリーンに当たります。
なんだか、とても不思議な感じです。
スライス(気味)だった球筋が、ドローとは言えないまでも
たまに左曲がりの球が出るようになりました。
距離も伸びますね! 一番手は違いそうです。
不安に感じたのは始めの数球で
記事にある通り、アプローチとフルショットのつながりが良く
これなら苦手なアプローチの距離感も乗り越えられそうです。
思い返してみると、体を止め、手で振っていると
無造作に動くヘッド、大きく変化するロフト、
これでは距離感掴めませんよね、反省する事、しきりです。
(以前、言われたことが今になって・・・です)
今までは 「動かす事ばかり」を考えていましたが、
今度は「動かさない事」なので、勇気(・・・度胸かも)さえ持てば
直ぐに出来ます。 誰にも簡単!とは言えませんが、
動かさない事は誰にも挑戦できるはずです。
まだ、ドライバーまでは到達出来ませんが、
次はフェアウェイウッドで挑戦しようと思っています。
とりあえず ご報告までに。
(店主)お手紙ありがとうございます。
一般的には
◯インパクトは ボールと正対して…とか
◯体を開くコト
◯アウトサイドインになるコト
◯ボールをよく見るコト
◯左サイドの壁
など 気が付かないうちに
インパクトで左サイドを止めるコトの『暗示』
をかけられているのかも知れません。
【達人リートレビノ式 インパクトはココだよ!】は
フルショット、ドライバーなどにも勿論ですが、
特に アプローチの距離感には特効薬と成り得ます。
仰る通り、からだを止めて 手で振るスイングは
管理できない 放り投げるようなヘッド で打つのですから
ヘッドスピードの管理が出来ません。
 動作とヘッドスピードに関係性が薄い です。
動作とヘッドスピードに関係性が薄い です。からだの回転で打てるようになると
自分の運動速度が そのままヘッドスピードになり、
ロフトやフェースの向きの変化 だけでなく
ヘッドの上下動も少なくなりますから
自分のモノにすれば 効果は絶大と思います。
ゴルフを始められた方に
この「達人リートレビノ式」を教えれば
終生、アプローチやショットに深く苦しまないで済む と
思うのですがね~。 冗談ですが、業界の陰謀かも…。
2020年8月22日土曜日
皆さんの目指しているゴルフスイングってコレですか❓
☞ハミングバードスポルテ本店
http://blog.livedoor.jp/hbs/
ゴルフスイングはその名の通り、
ゴルフクラブと言う道具を使って打ちます。
そして そのゴルフクラブには
距離や弾道、高さなどを決めるロフト角度など
いろいろな機能が付いており、
それを活かして、それを利用して
ボールを打つのを
『ゴルフ』スイング と呼ぶのだと思います。
これって
➀初めてゴルフをする人が
見よう見まねで 棒を振っている
➁先っちょをボールに当てようとする
✋この時点で 道具の機能 は
長さがある というコト
先端に打撃部分がある というコト
以外、動作を作るうえで考慮されていません。
➂ゴルフらしい動きに似せる
➃画像や動画を見て スイングらしいモノ にする
➄からだを使え と言われるから からだを回したフリをするが
棒を振っているの基礎に その量を増やしてるに過ぎず
からだ自体は打つコトにはあまり関係がない
この精度を上げていくコト が
皆さんの目指すゴルフスイング…ですか❓
ゴルフクラブの影響は想像以上!
☞ハミングバードスポルテ本店
http://blog.livedoor.jp/hbs/
丹念にレッスンを受けて スイングを造る人も例外
と言う人数です。
おおかた アバウトに 雑誌やネットで
その格好を刷り込み、なんとな~く
出た球を見ながら スイングを形成していく訳です。
つまり スイングにとっての先生 であり
生涯のアドバイザーは
『自分の持っているクラブで打つ』
○練習場で出る「弾道」 というコトに為ります。

先日の記事の続き… で言うと
知らないで使っている 練習場で大半の数を打つ
アイアンのシャフトが オーバースペックな相当硬いシャフト
だとしましょう。 実際にそうです
今や 安く売るため、安く買うため、 と
「硬いシャフト、スチールシャフトを使うほど上手」
という カルト宗教の教え を頑なに信じる日本のゴルファーの
ほぼ 全員が その手のスペック です。
硬いシャフトのアイアン には
ものすごく軽く、小振り
重心距離の短い「軟鉄のアイアンヘッド」が装着されています。
硬いシャフト、軽いヘッド のクラブ で
それ相応の距離、それ相応の高さ の球 を打つには
ある程度、速いヘッドスピードが必要 になるので
速いテンポ、速いリズム になり易くなります。
硬いシャフト、軽いヘッド のクラブは双方の相乗効果 もあり
テークバックが速く、早いリズムで 深く なり易い傾向 にあります。
よほど 機械的にスイングを造らない限り
(ジュニアが造っていくような 型を、数で、覚えるパターンです)
弾道を見ながら スイングの是非を構築していくと
速いテークバックの、深いトップの位置が形成されていきます。
雑誌などで かいつまんでみた スイング論 などでは
「からだをまわせ」
「左肩を入れろ」
などありますから 当然、それは助長されていく訳 です。
例外もある とは思いますが、
どうでしょう?
練習場で 自分の周りのゴルファーを見回してみて下さい。
大半が その通り ではありませんか?
これって その言葉の通り
「ゴルフクラブから レッスンを受けている」 のです。
大枚叩いて購入した 自分のゴルフクラブを使って
良い球、良い距離を打ちたい と思うのは
当たり前の感覚で 『自分のクラブを使って どう打つか」
という スイング創りの前提論は 絶対論 なのです。


 それは アプローチにも悪い意味で発揮されます。
それは アプローチにも悪い意味で発揮されます。
軽いヘッド、硬いシャフトのクラブで
ボールを打つには 速いスピードが必要です。
しかし 距離の加減 が要になる アプローチとは
半ば 相反する関係です。
本来、速度を遅くしても ヘッドの重量や
シャフトのたわみ~ヘッドの遅れ などによって
ボールは飛び、ボールは浮き、ボールは拾えます。
 しかし 硬いシャフトによって培われた
しかし 硬いシャフトによって培われた
ヘッドを返す打撃では
 練習場で言えば ボールとマットの間、
練習場で言えば ボールとマットの間、
 コースで言えば ボールと芝の間、
コースで言えば ボールと芝の間、
に ヘッドを滑り込ませなければなりません。
地面にあるボールを拾う ように打つ その打ち方は
イコール ロフトを寝かせて打つ、
クラブを薄べったくして その隙間に入れる その打ち方では
速い通過、急いでインパクトを終わらせないと
だふったり トップは当然、付いて回ります。
 ご存知
ご存知 とは思うのですが、
とは思うのですが、
ロフト「角度」を寝かす というコトは
イコール 同じ分量 バンス「角度」を増やす というコトで
入射を緩く取り ロフトを増やせば
ヘッドとボールが接触する前に
バンス部(ソール)が地面と 『必ず』 接触します。
形式上、ナイスショットもどき …特に練習場に置いて
そのナイスショットは 絶対にダふったショット
俗に言う 「いっちょ噛み」 の状態になります。
そのショットをしている多くのゴルファーは
自覚は無いかも知れませんが、
ロフトを増やして 上げ目、高めのボールを打つ場合、
遅い速度、インパクト付近で時間を喰えば
トップかダフリになってしまうので
インパクト付近の加速、
もしくは全体に速めのスイングは絶対に必要です。
しかし アプローチショットの距離加減は
ヘッドスピードであったり、動作速度 します。
そのアクセル加減で、スピード加減 で距離を調節するモノです。
インパクト付近の加速、
もしくは全体に速めのスイングが必要な アプローチ の
距離加減は ヘッドスピードや動作速度 『加減』 なのです。
言うなれば 古~~いスポーツカー のような扱いの難しい、
回転数が低すぎると ノッキングやエンストを起こしてしまう、
高回転を得意とする車で 枠のない狭い橋 を渡るような
曲がり角ばかりの狭い道を走るような そんな感覚 に近い のです。
コト この手の問題になると
厳しい言い方ですが、
余計な知識は満載なのに
肝心な知識が空白な状態であると
アプローチの練習を色々な形でするコトになります。
正しい クラブ扱いでは ヘッドは永遠にグリップを追い越しません。
しかし 使っているクラブ、使ってきたクラブによっては
ヘッドがグリップを追い越さないと ボールは飛ばず、
地面にあるボールは拾えず、スライスしか出なくなったりします。
問題なのは
ショット全体を ヘッドターンしないと打てない様な、
ヘッドを返さないと捕まらない様な シャフトの硬さ や
強く打たないと飛ばない ヘッドの軽さ によって
無自覚に作られてしまったコトがベースに合って、
そこから先 部位と言う意味ではない 小手先の技術で
対応するコトが 問題をより深みに追い込んでしまう というコトに
殆ど誰も、ゴルフの業界にいる人間ですら
気付いていないことが 一番の問題 だと思います。
丹念にレッスンを受けて スイングを造る人も例外
と言う人数です。
おおかた アバウトに 雑誌やネットで
その格好を刷り込み、なんとな~く
出た球を見ながら スイングを形成していく訳です。
つまり スイングにとっての先生 であり
生涯のアドバイザーは
『自分の持っているクラブで打つ』
○練習場で出る「弾道」 というコトに為ります。

先日の記事の続き… で言うと
知らないで使っている 練習場で大半の数を打つ
アイアンのシャフトが オーバースペックな相当硬いシャフト
だとしましょう。 実際にそうです

今や 安く売るため、安く買うため、 と
「硬いシャフト、スチールシャフトを使うほど上手」
という カルト宗教の教え を頑なに信じる日本のゴルファーの
ほぼ 全員が その手のスペック です。
硬いシャフトのアイアン には
ものすごく軽く、小振り
重心距離の短い「軟鉄のアイアンヘッド」が装着されています。
硬いシャフト、軽いヘッド のクラブ で
それ相応の距離、それ相応の高さ の球 を打つには
ある程度、速いヘッドスピードが必要 になるので
速いテンポ、速いリズム になり易くなります。
硬いシャフト、軽いヘッド のクラブは双方の相乗効果 もあり
テークバックが速く、早いリズムで 深く なり易い傾向 にあります。
よほど 機械的にスイングを造らない限り
(ジュニアが造っていくような 型を、数で、覚えるパターンです)
弾道を見ながら スイングの是非を構築していくと
速いテークバックの、深いトップの位置が形成されていきます。
雑誌などで かいつまんでみた スイング論 などでは
「からだをまわせ」
「左肩を入れろ」
などありますから 当然、それは助長されていく訳 です。
例外もある とは思いますが、
どうでしょう?
練習場で 自分の周りのゴルファーを見回してみて下さい。
大半が その通り ではありませんか?
これって その言葉の通り
「ゴルフクラブから レッスンを受けている」 のです。
大枚叩いて購入した 自分のゴルフクラブを使って
良い球、良い距離を打ちたい と思うのは
当たり前の感覚で 『自分のクラブを使って どう打つか」
という スイング創りの前提論は 絶対論 なのです。


 それは アプローチにも悪い意味で発揮されます。
それは アプローチにも悪い意味で発揮されます。軽いヘッド、硬いシャフトのクラブで
ボールを打つには 速いスピードが必要です。
しかし 距離の加減 が要になる アプローチとは
半ば 相反する関係です。
本来、速度を遅くしても ヘッドの重量や
シャフトのたわみ~ヘッドの遅れ などによって
ボールは飛び、ボールは浮き、ボールは拾えます。
 しかし 硬いシャフトによって培われた
しかし 硬いシャフトによって培われたヘッドを返す打撃では
 練習場で言えば ボールとマットの間、
練習場で言えば ボールとマットの間、 コースで言えば ボールと芝の間、
コースで言えば ボールと芝の間、に ヘッドを滑り込ませなければなりません。
地面にあるボールを拾う ように打つ その打ち方は
イコール ロフトを寝かせて打つ、
クラブを薄べったくして その隙間に入れる その打ち方では
速い通過、急いでインパクトを終わらせないと
だふったり トップは当然、付いて回ります。
 ご存知
ご存知 とは思うのですが、
とは思うのですが、ロフト「角度」を寝かす というコトは
イコール 同じ分量 バンス「角度」を増やす というコトで
入射を緩く取り ロフトを増やせば
ヘッドとボールが接触する前に
バンス部(ソール)が地面と 『必ず』 接触します。
形式上、ナイスショットもどき …特に練習場に置いて
そのナイスショットは 絶対にダふったショット
俗に言う 「いっちょ噛み」 の状態になります。
そのショットをしている多くのゴルファーは
自覚は無いかも知れませんが、
ロフトを増やして 上げ目、高めのボールを打つ場合、
遅い速度、インパクト付近で時間を喰えば
トップかダフリになってしまうので
インパクト付近の加速、
もしくは全体に速めのスイングは絶対に必要です。
しかし アプローチショットの距離加減は
ヘッドスピードであったり、動作速度 します。
そのアクセル加減で、スピード加減 で距離を調節するモノです。
インパクト付近の加速、
もしくは全体に速めのスイングが必要な アプローチ の
距離加減は ヘッドスピードや動作速度 『加減』 なのです。
言うなれば 古~~いスポーツカー のような扱いの難しい、
回転数が低すぎると ノッキングやエンストを起こしてしまう、
高回転を得意とする車で 枠のない狭い橋 を渡るような
曲がり角ばかりの狭い道を走るような そんな感覚 に近い のです。
コト この手の問題になると
厳しい言い方ですが、
余計な知識は満載なのに
肝心な知識が空白な状態であると
アプローチの練習を色々な形でするコトになります。
正しい クラブ扱いでは ヘッドは永遠にグリップを追い越しません。
しかし 使っているクラブ、使ってきたクラブによっては
ヘッドがグリップを追い越さないと ボールは飛ばず、
地面にあるボールは拾えず、スライスしか出なくなったりします。
問題なのは
ショット全体を ヘッドターンしないと打てない様な、
ヘッドを返さないと捕まらない様な シャフトの硬さ や
強く打たないと飛ばない ヘッドの軽さ によって
無自覚に作られてしまったコトがベースに合って、
そこから先 部位と言う意味ではない 小手先の技術で
対応するコトが 問題をより深みに追い込んでしまう というコトに
殆ど誰も、ゴルフの業界にいる人間ですら
気付いていないことが 一番の問題 だと思います。
ラウンド8-2
☞ハミングバードスポルテ本店
http://blog.livedoor.jp/hbs/
☞ハミングバード YouTube
https://www.youtube.com/user/HummingBirdSports?feature=mhee
☞ハミングバードFB
https://www.facebook.com/sporte.hummingbird
☞ハミングバードHP
http://www.hummingbird-sports.com/
2020年8月21日金曜日
Lee Trevino #pncfathersonchallenge #pncfathersonchallenge
☞ハミングバードスポルテ本店
http://blog.livedoor.jp/hbs/
☞ハミングバード YouTube
https://www.youtube.com/user/HummingBirdSports?feature=mhee
☞ハミングバードFB
https://www.facebook.com/sporte.hummingbird
☞ハミングバードHP
http://www.hummingbird-sports.com/
経典(仮)2
☞ハミングバードスポルテ本店
http://blog.livedoor.jp/hbs/
☞ハミングバード YouTube
https://www.youtube.com/user/HummingBirdSports?feature=mhee
☞ハミングバードFB
https://www.facebook.com/sporte.hummingbird
☞ハミングバードHP
http://www.hummingbird-sports.com/
ヘッドは遅らせて使うモノ 問題はグリップの遅れ
☞ハミングバードスポルテ本店
http://blog.livedoor.jp/hbs/
ゴルフを始めたばかりの人の多くは
ボールに当たるようになっても スライスに苦しみます。
その頃に ゴルフの先輩やら 自称上級者たちから
「振り遅れているから スライスするんだ」とか
「アウトサイドインに振るから スライスになるんだ」
「体が開いているから スライスするんだ」
のような 言葉を貰います。
これ…結構 呪いのように長いゴルフ人生に残るのです。
その中でも 今回は 昨日の記事の延長の
「振り遅れ」についてです。
物理的なスイング事情では
スイングでの クラブの横移動に対しては
重さの増す ヘッド部分は スイングの進行に対し
普通に遅れます。 遅れるのが正解です。
スライス。。。ボールに右回転が入るのは
ヘッドの移動してきた道に対し フェースが開いている
右を向いているからで
遅れている から スライス も
アウトサイドイン だから スライス も
からだが開いている から スライス も
テストの回答としては ◯はあげられません。
✘に限りなく近い ▲な状態・・・。
遅れ・・・は 二つの比較できるものがあるから 遅れ で
それがグリップなのか、体の進行(体の向き)なのかはっきりしませんが、
そのどちらであっても
ヘッドの進行に対し フェースが開いていなければ右回転は入りません。
遅れていても フック(左回転)を打つコトも十分可能です。
アウトサイドイン。。。
これは単に 打ち手のエゴに過ぎないのですが、
ボールに対して構えていても、
無機質なボール自身は構えや構えの向きは当然判りません。
構えに対し アウトサイドインに振っても
ボールに対しては その方向に振ったに過ぎず
それも ヘッド軌道に対して フェースが開いている(ロフトが付いている)コト
が 右回転の入る原因で ヘッド軌道そのものとは関係がありません。
からだの開き。。。に関しては言えば
言うまでもないのですが からだが開いても どんな球も出ます。
それも単に 物理的な問題で ヘッドの軌道に対し
ロフトが開いているコト/フェースが右を向いているコト が
右回転を生み出しているのです。
技術的な面で言えば
ヘッドはその重さから 当然遅れようとするのですが、
スイングは体の向きを変える 円運動 です。
体の向きを変えて グリップを動かす
そうすると シャフトでつながった ヘッドは動こうとしますが、
ヘッドそのものの重さや運動から 遅れようとするので
遅れが無い と仮定した 円周よりも
内回り、スイングの場合は 打ち手に近いトコロを付いて来よう とします。

無理にヘッドを そのヘッドの重さがない、遅れが無い とした
外周、クラブの長さ分の外周を動かそうとすることが
真の遅れ

 グリップの遅れ を生んでしまうのです。
グリップの遅れ を生んでしまうのです。
グリップが遅れず ヘッドだけが遅れ
その分内回りをし、下に下がれば
その遅れはロフトの立ちに替わりますが、
ヘッドを動かそうとして、グリップをからだの回転から遅らせてしまうと
ヘッドは開きます。 これが真の遅れです。
ヘッドという長さも含んだ重さを
無理やり人力で動かすのが正解なのか
その重さを 自然の法則に則り 利用するのが正解なのか
自分の頭で考えれば答えは遠くないと思いますが…
ここは正直、技術的な面と言うよりも
スイングはこうする という思い込みが作り出した
スイングの悪しき幻想のせい だと私は思います。
ゴルフを始めたばかりの人の多くは
ボールに当たるようになっても スライスに苦しみます。
その頃に ゴルフの先輩やら 自称上級者たちから
「振り遅れているから スライスするんだ」とか
「アウトサイドインに振るから スライスになるんだ」
「体が開いているから スライスするんだ」
のような 言葉を貰います。
これ…結構 呪いのように長いゴルフ人生に残るのです。
その中でも 今回は 昨日の記事の延長の
「振り遅れ」についてです。
物理的なスイング事情では
スイングでの クラブの横移動に対しては
重さの増す ヘッド部分は スイングの進行に対し
普通に遅れます。 遅れるのが正解です。
スライス。。。ボールに右回転が入るのは
ヘッドの移動してきた道に対し フェースが開いている
右を向いているからで
遅れている から スライス も
アウトサイドイン だから スライス も
からだが開いている から スライス も
テストの回答としては ◯はあげられません。
✘に限りなく近い ▲な状態・・・。
遅れ・・・は 二つの比較できるものがあるから 遅れ で
それがグリップなのか、体の進行(体の向き)なのかはっきりしませんが、
そのどちらであっても
ヘッドの進行に対し フェースが開いていなければ右回転は入りません。
遅れていても フック(左回転)を打つコトも十分可能です。
アウトサイドイン。。。
これは単に 打ち手のエゴに過ぎないのですが、
ボールに対して構えていても、
無機質なボール自身は構えや構えの向きは当然判りません。
構えに対し アウトサイドインに振っても
ボールに対しては その方向に振ったに過ぎず
それも ヘッド軌道に対して フェースが開いている(ロフトが付いている)コト
が 右回転の入る原因で ヘッド軌道そのものとは関係がありません。
からだの開き。。。に関しては言えば
言うまでもないのですが からだが開いても どんな球も出ます。
それも単に 物理的な問題で ヘッドの軌道に対し
ロフトが開いているコト/フェースが右を向いているコト が
右回転を生み出しているのです。
技術的な面で言えば
ヘッドはその重さから 当然遅れようとするのですが、
スイングは体の向きを変える 円運動 です。
体の向きを変えて グリップを動かす
そうすると シャフトでつながった ヘッドは動こうとしますが、
ヘッドそのものの重さや運動から 遅れようとするので
遅れが無い と仮定した 円周よりも
内回り、スイングの場合は 打ち手に近いトコロを付いて来よう とします。

無理にヘッドを そのヘッドの重さがない、遅れが無い とした
外周、クラブの長さ分の外周を動かそうとすることが
真の遅れ


 グリップの遅れ を生んでしまうのです。
グリップの遅れ を生んでしまうのです。グリップが遅れず ヘッドだけが遅れ
その分内回りをし、下に下がれば
その遅れはロフトの立ちに替わりますが、
ヘッドを動かそうとして、グリップをからだの回転から遅らせてしまうと
ヘッドは開きます。 これが真の遅れです。
ヘッドという長さも含んだ重さを
無理やり人力で動かすのが正解なのか
その重さを 自然の法則に則り 利用するのが正解なのか
自分の頭で考えれば答えは遠くないと思いますが…
ここは正直、技術的な面と言うよりも
スイングはこうする という思い込みが作り出した
スイングの悪しき幻想のせい だと私は思います。
ラウンド8-2
☞ハミングバードスポルテ本店
http://blog.livedoor.jp/hbs/
☞ハミングバード YouTube
https://www.youtube.com/user/HummingBirdSports?feature=mhee
☞ハミングバードFB
https://www.facebook.com/sporte.hummingbird
☞ハミングバードHP
http://www.hummingbird-sports.com/
2020年8月20日木曜日
反発係数こぼれ話 ロフト角度の経緯
☞ハミングバードスポルテ本店
http://blog.livedoor.jp/hbs/
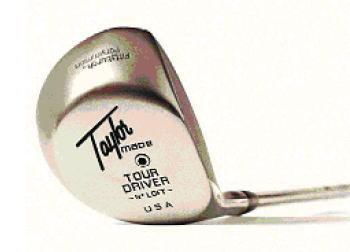
加えて、まだメタル素材のヘッドを大量生産する
技術力が低く、ネック周りが破損するトラブルを大量に
秘めた当初のドライバーはネックが太く、長く
故に重心位置が高く短い
構造的に よりスピンの入りやすいものだった。
いまでこそ 大型ドライバーの重心距離は35mmを超えるが
開発当初のメタルヘッドは20㎜を下回るものも多く
パーシモンよりも二回り位「小振り」なものであった。
今となってはそれが分かるけれど
当初は 飛距離が出ない、スピンや高さばかりが増える
メタルヘッドを一般化する方法として
12.13度だったロフト角度を 9.10.11度にしたことで
その問題を解決した
それが 現代の一般的なロフト構成の始まり だった
ということなのです。
理論上は既に反発係数の考えに相当する
インピーダンス理論は存在していて
それを応用すれば 別な方法によって
その問題を解決することは出来た(結果論ではあるね)
それによって 一般的なドライバーヘッドのロフトが
パーシモンのそれを継続するチャンスもあった。
まあ でも、まだまだそのインピーダンス理論や
重心位置と球質の関係は工業技術の問題も伴うが
当時にはまだ苦しかったろうね。
チタンも含めたメタル系のドライバーの
一般的なロフトは 9.10.11度・・・
そこに行きついた経緯のお話。
( ゚Д゚) ( ゚Д゚) ( ゚Д゚) ( ゚Д゚)
通常のショットでは
ボールはその歪み、その復元に打撃のエネルギーの
3割前後も消費してしまう。
反発係数とは
ボールの歪み率と出来るだけ近くなる構造や素材で
ボールを打撃するとボールの歪みが抑えられ、
エネルギーロスが少なくなり、ボールの初速が速くなる、
ということ。
ボールが歪むと総じてロフト効果が増えやすく
エネルギーのロスだけでなく、スピン、打ちだし角度ともに
増加の傾向が強い。
反発係数と名付けたところがなんだか誤解を生みやすいが
この反発係数 一番高くなる素材は
その名称とは裏腹に パーシモン 木の素材である。
ルールの設定されているのは 0.86 という数値であるが
パーシモン素材のドライバーの多くが 0.9 を超え
中には 0.93 という数値のものまである。
イメージで言うと
反発 するのとは全く真逆な パーシモンヘッド が
数値が高いというのは ブラックユーモアみたいではある。
ボールのスピンとスピード というもので見ると
パーシモンヘッドはスピンがとても入りにくく
その分ボールスピードになり易い という特性をもっている。
がゆえに パーシモンヘッドのドライバーの
一般的なロフトは 11~13度
ドライバー(本来はドライビングクラブ)と
規定されるのは 15度未満のロフトのもの
と由縁でもある。
世界的にゴルフがブーム傾向にあり、
パーシモンドライバーの素材の確保や
ドライバーに適う目や節などの希少性、
工業技術の向上による大量生産の可能化などから
メタル素材のドライバーに推移していくのだけど
メタルの素材特性を活かして
という 科学的な見地にはまだ至らず
パーシモンのその形状だけをメタル素材でコピーする
ということから始まる。
メタルが一般化した代表作である
テイラーメイドのそれを
ピッツバーグ・パーシモンと呼んだりもした。
反発係数の低い メタル素材のドライバーを
パーシモン素材の時の一般的なロフトで製品化すれば
ボールはスピンばかりが増え、距離になりにくい。
実はそれこそ 反発係数の問題もあったのだ。
一般的なロフトは 9.10.11度・・・
そこに行きついた経緯のお話。
( ゚Д゚) ( ゚Д゚) ( ゚Д゚) ( ゚Д゚)
通常のショットでは
ボールはその歪み、その復元に打撃のエネルギーの
3割前後も消費してしまう。
反発係数とは
ボールの歪み率と出来るだけ近くなる構造や素材で
ボールを打撃するとボールの歪みが抑えられ、
エネルギーロスが少なくなり、ボールの初速が速くなる、
ということ。
ボールが歪むと総じてロフト効果が増えやすく
エネルギーのロスだけでなく、スピン、打ちだし角度ともに
増加の傾向が強い。
反発係数と名付けたところがなんだか誤解を生みやすいが
この反発係数 一番高くなる素材は
その名称とは裏腹に パーシモン 木の素材である。
ルールの設定されているのは 0.86 という数値であるが
パーシモン素材のドライバーの多くが 0.9 を超え
中には 0.93 という数値のものまである。
イメージで言うと
反発 するのとは全く真逆な パーシモンヘッド が
数値が高いというのは ブラックユーモアみたいではある。
ボールのスピンとスピード というもので見ると
パーシモンヘッドはスピンがとても入りにくく
その分ボールスピードになり易い という特性をもっている。
がゆえに パーシモンヘッドのドライバーの
一般的なロフトは 11~13度
ドライバー(本来はドライビングクラブ)と
規定されるのは 15度未満のロフトのもの
と由縁でもある。
世界的にゴルフがブーム傾向にあり、
パーシモンドライバーの素材の確保や
ドライバーに適う目や節などの希少性、
工業技術の向上による大量生産の可能化などから
メタル素材のドライバーに推移していくのだけど
メタルの素材特性を活かして
という 科学的な見地にはまだ至らず
パーシモンのその形状だけをメタル素材でコピーする
ということから始まる。
メタルが一般化した代表作である
テイラーメイドのそれを
ピッツバーグ・パーシモンと呼んだりもした。
反発係数の低い メタル素材のドライバーを
パーシモン素材の時の一般的なロフトで製品化すれば
ボールはスピンばかりが増え、距離になりにくい。
実はそれこそ 反発係数の問題もあったのだ。
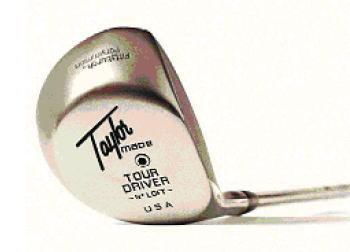
加えて、まだメタル素材のヘッドを大量生産する
技術力が低く、ネック周りが破損するトラブルを大量に
秘めた当初のドライバーはネックが太く、長く
故に重心位置が高く短い
構造的に よりスピンの入りやすいものだった。
いまでこそ 大型ドライバーの重心距離は35mmを超えるが
開発当初のメタルヘッドは20㎜を下回るものも多く
パーシモンよりも二回り位「小振り」なものであった。
今となってはそれが分かるけれど
当初は 飛距離が出ない、スピンや高さばかりが増える
メタルヘッドを一般化する方法として
12.13度だったロフト角度を 9.10.11度にしたことで
その問題を解決した
それが 現代の一般的なロフト構成の始まり だった
ということなのです。
理論上は既に反発係数の考えに相当する
インピーダンス理論は存在していて
それを応用すれば 別な方法によって
その問題を解決することは出来た(結果論ではあるね)
それによって 一般的なドライバーヘッドのロフトが
パーシモンのそれを継続するチャンスもあった。
まあ でも、まだまだそのインピーダンス理論や
重心位置と球質の関係は工業技術の問題も伴うが
当時にはまだ苦しかったろうね。
2020年8月19日水曜日
ラウンド8
☞ハミングバードスポルテ本店
http://blog.livedoor.jp/hbs/
☞ハミングバード YouTube
https://www.youtube.com/user/HummingBirdSports?feature=mhee
☞ハミングバードFB
https://www.facebook.com/sporte.hummingbird
☞ハミングバードHP
http://www.hummingbird-sports.com/
アドレス🔵スタンスの向き
☞ハミングバードスポルテ本店
http://blog.livedoor.jp/hbs/
スタンス アドレスには大切な二つのチェックポイントがあります。
これはご存知だと思いますが
❶スタンスはターゲットと平行
であって スタンスをターゲットに向けるのではありません。
疲れてきたり、急いでいたりすると
無意識にそうなりがち…ですので ご注意ください。

スタンス自体をターゲットに向かって取ってしまう と
結果として 大きく右を向いて アドレスをしてしまうことになります。
ゴルフを始めたばかり の人はこれ多いです。
これで練習すると
右を向いて引っかける というのが自分のスタンダードになってしまう上
例えば 見た目上 左の足かかと付近にボールを置いているようでも
実際には ずっと外、ずっと左に置いているコトになり
当たらない、届かない ひっかけが激しくなる が故に
ボールをグッと中に入れて 構えることになります。
ここまでくると結構複雑です。
ちょっと時間かけても スタンスも向きは修正しておきたいです。
❷スタンスの向きは両かかとのラインで
多くのゴルファーは
スタンスの向きの基準をつま先 でとりますが
それはちょっとチェックし直した方が良いです。
右打ちのゴルファーの場合 左足
左の足、㊧の靴の方がつま先を開いてるケースが多く
その状態で 両つま先がターゲットと平行…
というコトになると
実際にはやや右を向いて打っているコトになります。
つま先の開き具合は
ある意味傾斜への対処 にもなります。
ですので つま先基準でスタンスの向きを作ってしまうと
コースへ出た時、その傾斜、傾斜具合で
ボールの位置が動いてしまう というコトになるので
かかとでスタンスの向きを取ることに慣れましょう
スタンス アドレスには大切な二つのチェックポイントがあります。
これはご存知だと思いますが
❶スタンスはターゲットと平行
であって スタンスをターゲットに向けるのではありません。
疲れてきたり、急いでいたりすると
無意識にそうなりがち…ですので ご注意ください。

スタンス自体をターゲットに向かって取ってしまう と
結果として 大きく右を向いて アドレスをしてしまうことになります。
ゴルフを始めたばかり の人はこれ多いです。
これで練習すると
右を向いて引っかける というのが自分のスタンダードになってしまう上
例えば 見た目上 左の足かかと付近にボールを置いているようでも
実際には ずっと外、ずっと左に置いているコトになり
当たらない、届かない ひっかけが激しくなる が故に
ボールをグッと中に入れて 構えることになります。
ここまでくると結構複雑です。
ちょっと時間かけても スタンスも向きは修正しておきたいです。
❷スタンスの向きは両かかとのラインで
多くのゴルファーは
スタンスの向きの基準をつま先 でとりますが
それはちょっとチェックし直した方が良いです。
右打ちのゴルファーの場合 左足
左の足、㊧の靴の方がつま先を開いてるケースが多く
その状態で 両つま先がターゲットと平行…
というコトになると
実際にはやや右を向いて打っているコトになります。
つま先の開き具合は
ある意味傾斜への対処 にもなります。
ですので つま先基準でスタンスの向きを作ってしまうと
コースへ出た時、その傾斜、傾斜具合で
ボールの位置が動いてしまう というコトになるので
かかとでスタンスの向きを取ることに慣れましょう

2020年8月18日火曜日
両手離し(スプリットハンド)ドリル
☞ハミングバードスポルテ本店
http://blog.livedoor.jp/hbs/
☞ハミングバード YouTube
https://www.youtube.com/user/HummingBirdSports?feature=mhee
☞ハミングバードFB
https://www.facebook.com/sporte.hummingbird
☞ハミングバードHP
http://www.hummingbird-sports.com/
アプローチの延長線~でフルショットを
☞ハミングバードスポルテ本店
http://blog.livedoor.jp/hbs/
飛距離不足やスライスに悩んでいる、すべての人に
当てはまる、上手く行くとは限りませんが、
弾道が低くて苦しんでいる人には適合しませんが、
スライスや弾道が高い人には 一つの打開策 になると思います。

❶まずは ランニングアプローチから始めましょう
ここのポイントは からだを回すコト です。
からだをまわす のは 肩ではなく
お腹、そのポッコリお腹の向きを変えましょう
右を向けるだけでなく やや下向き、
気持ちだけでもいいですから「下向き」に右を変えるコト がポイントです。
脚のサポートもありますが、腰回りと言うよりは
お腹周りを使って 右向きを作ります。
❷ …①上記の延長です
 肩を揺さぶらない
肩を揺さぶらない
 左肩「を」入れようとしない
左肩「を」入れようとしない
 左手・左肩でテークバックを取ろうとしない
左手・左肩でテークバックを取ろうとしない
その目安になるのが フェースの向きです。
帰り(ダウンスイング)は兎も角、行きは重要な ポイント
ポイント
軌道に対し、常時 ヘッドはスクエアな状況を造ります。
ボールから始める テークアウェイでは
軌道は 右上方に移動する訳ですから
その軌道に対し フェースは逆向き~ボールを、下向きのまま
見続けて 移動していく感じです。
肩や左腕で行うと フェースが上を向くか
前傾姿勢分の斜め移動ラインよりもヘッドは下がります
少なくとも 見える範囲内 そこは注意してみましょう。
 ❸これも ❷の派生編ですが、
❸これも ❷の派生編ですが、
アプローチだけでなく フルショットであっても
ヘッドを下げる人が多くいます。
ヘッドを下げる とは
腕が固定の状態、腕を動かさなくても
胴体が右を向けば、前傾姿勢通りに
グリップも、ヘッドも、回転分、高くなります。(地面から離れます)
アドレスのグリップとヘッドの関係は
前傾しているから ヘッドの方が下にある錯覚を抱きますが、
実際には ヘッドの方がグリップよりも高い位置にあるので、
グリップの通るラインの 若干上側をヘッドは移動する筈 です。
です。
それを 下のラインを通してしまうと
ヘッドを下げた状態になるので トップで無意識に体を起こしたり
ダウンスイング以降で ヘッドを上げる、つらないといけなくなり
ミスの原因、ロフトを立てられない原因に成り得ます。
❹アプローチから ハーフ~フルショットに移行するのも
グリップの高さを取るだけ、ヘッドを高くする意識は要りません。
アプローチとフルショットの違いは グリップの高さ だけ です。
❺アプローチであっても フルショットであっても
前傾姿勢分(右サイドが高くなっている分)
常時、シャットフェース が望ましい です。
やり過ぎ もなんですが、練習として慣れていくのには
意識では フェースが地面に向いている位でも いいかも しれません。

ランニングアプローチでボールを打てていれば
グリップの高さを変える…だけですから
切り返し~ダウンスイング以降も 全く同じ です。
フルショットも含め スピードのコントロールをする だけです。
スピードを上げると モノの重さは増します。
それも含め ボールをさばくインパクトポイントのグリップの通過点 を
左にずらしたい訳ですが、
グリップを高くすると クラブの、ヘッドの構造上、
意識しなくとも、自然とシャフトは起きます。
その分、クラブ全体の重さはグリップの移動に使い易くなりますから
ものすごく 大きな 左へのズレの意識は要らない かも知れません。
飛距離不足やスライスに悩んでいる、すべての人に
当てはまる、上手く行くとは限りませんが、
弾道が低くて苦しんでいる人には適合しませんが、
スライスや弾道が高い人には 一つの打開策 になると思います。

❶まずは ランニングアプローチから始めましょう
ここのポイントは からだを回すコト です。
からだをまわす のは 肩ではなく
お腹、そのポッコリお腹の向きを変えましょう

右を向けるだけでなく やや下向き、
気持ちだけでもいいですから「下向き」に右を変えるコト がポイントです。
脚のサポートもありますが、腰回りと言うよりは
お腹周りを使って 右向きを作ります。
❷ …①上記の延長です
 肩を揺さぶらない
肩を揺さぶらない 左肩「を」入れようとしない
左肩「を」入れようとしない 左手・左肩でテークバックを取ろうとしない
左手・左肩でテークバックを取ろうとしないその目安になるのが フェースの向きです。
帰り(ダウンスイング)は兎も角、行きは重要な
 ポイント
ポイント軌道に対し、常時 ヘッドはスクエアな状況を造ります。
ボールから始める テークアウェイでは
軌道は 右上方に移動する訳ですから
その軌道に対し フェースは逆向き~ボールを、下向きのまま
見続けて 移動していく感じです。
肩や左腕で行うと フェースが上を向くか
前傾姿勢分の斜め移動ラインよりもヘッドは下がります
少なくとも 見える範囲内 そこは注意してみましょう。
 ❸これも ❷の派生編ですが、
❸これも ❷の派生編ですが、アプローチだけでなく フルショットであっても
ヘッドを下げる人が多くいます。
ヘッドを下げる とは
腕が固定の状態、腕を動かさなくても
胴体が右を向けば、前傾姿勢通りに
グリップも、ヘッドも、回転分、高くなります。(地面から離れます)
アドレスのグリップとヘッドの関係は
前傾しているから ヘッドの方が下にある錯覚を抱きますが、
実際には ヘッドの方がグリップよりも高い位置にあるので、
グリップの通るラインの 若干上側をヘッドは移動する筈
 です。
です。それを 下のラインを通してしまうと
ヘッドを下げた状態になるので トップで無意識に体を起こしたり
ダウンスイング以降で ヘッドを上げる、つらないといけなくなり
ミスの原因、ロフトを立てられない原因に成り得ます。
❹アプローチから ハーフ~フルショットに移行するのも
グリップの高さを取るだけ、ヘッドを高くする意識は要りません。
アプローチとフルショットの違いは グリップの高さ だけ です。
❺アプローチであっても フルショットであっても
前傾姿勢分(右サイドが高くなっている分)
常時、シャットフェース が望ましい です。
やり過ぎ もなんですが、練習として慣れていくのには
意識では フェースが地面に向いている位でも いいかも しれません。

ランニングアプローチでボールを打てていれば
グリップの高さを変える…だけですから
切り返し~ダウンスイング以降も 全く同じ です。
フルショットも含め スピードのコントロールをする だけです。
スピードを上げると モノの重さは増します。
それも含め ボールをさばくインパクトポイントのグリップの通過点 を
左にずらしたい訳ですが、
グリップを高くすると クラブの、ヘッドの構造上、
意識しなくとも、自然とシャフトは起きます。
その分、クラブ全体の重さはグリップの移動に使い易くなりますから
ものすごく 大きな 左へのズレの意識は要らない かも知れません。
2020年8月17日月曜日
アプローチショット SW-30/50/80▲
☞ハミングバードスポルテ本店
http://blog.livedoor.jp/hbs/
☞ハミングバード YouTube
https://www.youtube.com/user/HummingBirdSports?feature=mhee
☞ハミングバードFB
https://www.facebook.com/sporte.hummingbird
☞ハミングバードHP
http://www.hummingbird-sports.com/
重心距離をゼロに❔
☞ハミングバードスポルテ本店
http://blog.livedoor.jp/hbs/
ゴルフクラブ、打撃部分であるゴルフクラブ『ヘッド』には
ボールを遠くに、出来るだけ思った通りの方向、弾道に
繰り返し打ち易くする為、重心位置と言うのが存在します。
重心位置と言うのはどんなものか というと
それは クラブヘッドに点として存在しているのですが、
(目で見えたり、印が付いている訳ではありません)
ヘッドの重さの中心点のコトを指し、
野球のバットやテニスのラケットのように
握った棒の 延長線上に打点が存在せず、
L型にズレたところの存在するのが その特徴です。

ちょっと困った点ではありますが、
最近のゴルフクラブの傾向として、
長いドライバーなどのウッド系は そのズレが40mm
短いアイアン系のモノが 35mm と
少しですが 差が有ります。 (逆ならより使い易いですけどね)
それを一般的には 重心位置の中でも重心距離 と呼んでいます。
感覚的には 棒そのものではなく、棒から 3cmから4cm
離れたところで打つ そう言う感じです。
(柔らかいシャフトであれば その必要ないんですけどね)
では、その逆に その重心距離が無かったら、
棒の延長線上に打点が有ったら、どうなるのでしょう。
実はこれ、過去に試したことがあって
ゴルフクラブテスト個人史上、最高、最低の
ものすごく怖い体験をしています…
二度としません…。
重心距離がゼロ にゴルフクラブは
過去に数度、通販などで販売されているのですが…
その都度、かなり短期間に消滅しています。
と。。。いうコトでよほどネットを探さないと現存していない と言う代物。
その重心距離がゼロのクラブ、必ずドライバーなのですが、
ドライバーだけ ってトコロにもヒントがあったりします。
ってトコロにもヒントがあったりします。
まず よほど構造、形状を考え、違うモノ にしない限り、
重心距離がゼロのクラブには ライ角度 と言うモノが設定出来ません。
ロフトの立ったクラブであれば まだ良いですが、
ロフトの大きな、寝たクラブとライ角度を併用すると
二度打ちや自分に向かってボールが飛び出てくる可能性があり
上手く打てる、打てない、飛ぶ、飛ばないの前に
安全性の問題が出てきます。
ですので 全番手にそう言う構造を採用し難いのです。
飛ばす、上げる、距離差を生む、方向 を同時に達成するには
重心距離-構造は必須というコトなのです。

また、多くの人がヘッドは回転させて打つ と言う認識を持っています。
重心距離が存在しないと、スイング中
ヘッドがどこを向いていても、どのような状態でも
感覚、感触として どうなっているのか把握するのが難しく
ヘッドを回転させるにしても、ヘッドの回転のタイミング、度合い、速度
これを一定させる目安が掴めません。
●上手くボールに当たる姿勢と
 クラブのどこかの角がボールに向かっている、
クラブのどこかの角がボールに向かっている、
 フェースが自分の方を向いている、
フェースが自分の方を向いている、
それらの状況も 感触的な差異がないのです。
同時に、上記の安全上の問題が絡んでくるので
直ぐに回収されてしまったモノ もありました。
クラブヘッドに重心距離があるコトで
どう構え、どう振り上げ、どう振り下ろすか 把握するコトが出来る、
本当ならば、そこに 運動(移動)速度を上げた時のみ、
その重心距離が解消できる ⇒エネルギー伝達効率が良い ですから
柔らかいシャフトがベターなんですけどね。
ゴルフクラブ、打撃部分であるゴルフクラブ『ヘッド』には
ボールを遠くに、出来るだけ思った通りの方向、弾道に
繰り返し打ち易くする為、重心位置と言うのが存在します。
重心位置と言うのはどんなものか というと
それは クラブヘッドに点として存在しているのですが、
(目で見えたり、印が付いている訳ではありません)
ヘッドの重さの中心点のコトを指し、
野球のバットやテニスのラケットのように
握った棒の 延長線上に打点が存在せず、
L型にズレたところの存在するのが その特徴です。

ちょっと困った点ではありますが、
最近のゴルフクラブの傾向として、
長いドライバーなどのウッド系は そのズレが40mm
短いアイアン系のモノが 35mm と
少しですが 差が有ります。 (逆ならより使い易いですけどね)
それを一般的には 重心位置の中でも重心距離 と呼んでいます。
感覚的には 棒そのものではなく、棒から 3cmから4cm
離れたところで打つ そう言う感じです。
(柔らかいシャフトであれば その必要ないんですけどね)
では、その逆に その重心距離が無かったら、
棒の延長線上に打点が有ったら、どうなるのでしょう。
実はこれ、過去に試したことがあって
ゴルフクラブテスト個人史上、最高、最低の
ものすごく怖い体験をしています…
二度としません…。
重心距離がゼロ にゴルフクラブは
過去に数度、通販などで販売されているのですが…
その都度、かなり短期間に消滅しています。
と。。。いうコトでよほどネットを探さないと現存していない と言う代物。
その重心距離がゼロのクラブ、必ずドライバーなのですが、
ドライバーだけ
 ってトコロにもヒントがあったりします。
ってトコロにもヒントがあったりします。まず よほど構造、形状を考え、違うモノ にしない限り、
重心距離がゼロのクラブには ライ角度 と言うモノが設定出来ません。
ロフトの立ったクラブであれば まだ良いですが、
ロフトの大きな、寝たクラブとライ角度を併用すると
二度打ちや自分に向かってボールが飛び出てくる可能性があり
上手く打てる、打てない、飛ぶ、飛ばないの前に
安全性の問題が出てきます。
ですので 全番手にそう言う構造を採用し難いのです。
飛ばす、上げる、距離差を生む、方向 を同時に達成するには
重心距離-構造は必須というコトなのです。

また、多くの人がヘッドは回転させて打つ と言う認識を持っています。
重心距離が存在しないと、スイング中
ヘッドがどこを向いていても、どのような状態でも
感覚、感触として どうなっているのか把握するのが難しく
ヘッドを回転させるにしても、ヘッドの回転のタイミング、度合い、速度
これを一定させる目安が掴めません。
●上手くボールに当たる姿勢と
 クラブのどこかの角がボールに向かっている、
クラブのどこかの角がボールに向かっている、 フェースが自分の方を向いている、
フェースが自分の方を向いている、それらの状況も 感触的な差異がないのです。
同時に、上記の安全上の問題が絡んでくるので
直ぐに回収されてしまったモノ もありました。
クラブヘッドに重心距離があるコトで
どう構え、どう振り上げ、どう振り下ろすか 把握するコトが出来る、
本当ならば、そこに 運動(移動)速度を上げた時のみ、
その重心距離が解消できる ⇒エネルギー伝達効率が良い ですから
柔らかいシャフトがベターなんですけどね。
Improve Putting
☞ハミングバードスポルテ本店
http://blog.livedoor.jp/hbs/
☞ハミングバード YouTube
https://www.youtube.com/user/HummingBirdSports?feature=mhee
☞ハミングバードFB
https://www.facebook.com/sporte.hummingbird
☞ハミングバードHP
http://www.hummingbird-sports.com/
2020年8月16日日曜日
ゴルフクラブ選びの注意点 シャフトの硬さ
☞ハミングバードスポルテ本店
http://blog.livedoor.jp/hbs/
シャフトの硬さ は ヘッドの感じ難さ でもあります。

同じ長さ、同じヘッドの重量が装着されている場合、
シャフトの柔らかいモノのほうが
ヘッドの位置や姿勢など感じやすく
~ヘッド、ヘッドの重さを大事に使おうとするスイング~を
覚えやすいモノです。
例外もない…とは言えませんが、
シャフトの硬いモノを使うゴルファーほど
「シャフトはしならせて使う」と言いがちで
『なら 始めから 柔らかいモノを使えばいいじゃん!』
とハミングバードは感じます。
シャフトを意図的にしならせ、しなり戻す のは
ゴルフクラブという 上下左右の角度が重要な道具にとって
とても難易度の高い打撃を要求されることになります。
確かに そうやってゴルフクラブを扱ったほうが
"充実感"は味わえるかもしれませんが、
練習に時間も頻度も割けない 普通のゴルファーには
かなり大変です。

とても残念ですが、オジサンゴルファーの体力は日増しに劣化します。
今日 新しく購入するクラブは
今日から未来にかけて使うクラブで
今日だけ使うのではありません。
体力にとって、 今日 は過去の産物でもあり、
長く楽しんでいくのには シャフトの硬い
オーバースペックを選択して良いことは何もありません。
現在のゴルフクラブ事情は
売れない、売れない の連続のため
売る側の事情で 特に売れ行きの悪いアイアンセットは
本数も絞り、単価を安く抑えられるスチールシャフトを採用せざる
を得なくなっています。
軽量であろうがなかろうが
スチールシャフトの抱える問題は
実は大変深刻です。
スチールシャフトとグラファイトシャフトの大きな違いはかなりあります。
主に 硬さ と 強度 と ヘッド重量 です。
スチールシャフトは 強度が低いため、
柔らかいモノを作ることが出来ません。
5番アイアンで 頑張っても 振動数270cpm 程度が
柔らかさの限界…平均的には280cpm以上 でしょう。
長さの変化と硬さ(振動数)の変化から考えると
この硬さが 適合するドライバー(45インチ)は 260cpm
平均的な オジサンゴルファーにとって
使いやすい ドライバーの硬さは 220~230cpm
(これでも十分硬いですが…)
アイアンに合わせて 260cpm のドライバー ・・・
これでは硬すぎて飛ばないだけでなく
体も痛め、スイングも悪くなります。

となると ドライバーはドライバー
アイアンはアイアン と別なものと考えなくてはならず
ボールの置く位置やタイミングなど
もともと複雑なスイングがより混迷を深める原因になります。
また スチールシャフトの場合、
細くなり、負荷のかかりやすい先端部を補強するのは
金属の厚み でするしかないので
グラファイトの比べ 重いヘッドが装着できません。
その差は 20g以上 あるのです。
ドライバーやウッドに比べ
はるかに硬いシャフトの装着されたアイアン
シャフトも硬いのでヘッドも軽く感じますが、
実際に グラファイトのウッド系に比べると
20g以上も軽めのヘッドがつけられています。
悪いことに アイアンは軟鉄全盛 の時代ですから
ヘッド自体も小ぶりです。
シャフトが硬く、クラブも短いほうのアイアンに軽い小ぶりなヘッド が付き
シャフトが柔らかく、クラブも長いほうのウッドに大型ヘッドが装着…
☞こんな組み合わせ うまく行く筈がない…というか
うまく行く可能性はとても低い組み合わせ…なのです。
故に…実はドライバーに苦しんでいる人の
本当の原因は それと組み合わせるアイアン にあるかもしれない…のです。
シャフトの硬さ は ヘッドの感じ難さ でもあります。

同じ長さ、同じヘッドの重量が装着されている場合、
シャフトの柔らかいモノのほうが
ヘッドの位置や姿勢など感じやすく
~ヘッド、ヘッドの重さを大事に使おうとするスイング~を
覚えやすいモノです。
例外もない…とは言えませんが、
シャフトの硬いモノを使うゴルファーほど
「シャフトはしならせて使う」と言いがちで
『なら 始めから 柔らかいモノを使えばいいじゃん!』
とハミングバードは感じます。
シャフトを意図的にしならせ、しなり戻す のは
ゴルフクラブという 上下左右の角度が重要な道具にとって
とても難易度の高い打撃を要求されることになります。
確かに そうやってゴルフクラブを扱ったほうが
"充実感"は味わえるかもしれませんが、
練習に時間も頻度も割けない 普通のゴルファーには
かなり大変です。

とても残念ですが、オジサンゴルファーの体力は日増しに劣化します。
今日 新しく購入するクラブは
今日から未来にかけて使うクラブで
今日だけ使うのではありません。
体力にとって、 今日 は過去の産物でもあり、
長く楽しんでいくのには シャフトの硬い
オーバースペックを選択して良いことは何もありません。
現在のゴルフクラブ事情は
売れない、売れない の連続のため
売る側の事情で 特に売れ行きの悪いアイアンセットは
本数も絞り、単価を安く抑えられるスチールシャフトを採用せざる
を得なくなっています。
軽量であろうがなかろうが
スチールシャフトの抱える問題は
実は大変深刻です。
スチールシャフトとグラファイトシャフトの大きな違いはかなりあります。
主に 硬さ と 強度 と ヘッド重量 です。
スチールシャフトは 強度が低いため、
柔らかいモノを作ることが出来ません。
5番アイアンで 頑張っても 振動数270cpm 程度が
柔らかさの限界…平均的には280cpm以上 でしょう。
長さの変化と硬さ(振動数)の変化から考えると
この硬さが 適合するドライバー(45インチ)は 260cpm
平均的な オジサンゴルファーにとって
使いやすい ドライバーの硬さは 220~230cpm
(これでも十分硬いですが…)
アイアンに合わせて 260cpm のドライバー ・・・
これでは硬すぎて飛ばないだけでなく
体も痛め、スイングも悪くなります。

となると ドライバーはドライバー
アイアンはアイアン と別なものと考えなくてはならず
ボールの置く位置やタイミングなど
もともと複雑なスイングがより混迷を深める原因になります。
また スチールシャフトの場合、
細くなり、負荷のかかりやすい先端部を補強するのは
金属の厚み でするしかないので
グラファイトの比べ 重いヘッドが装着できません。
その差は 20g以上 あるのです。
ドライバーやウッドに比べ
はるかに硬いシャフトの装着されたアイアン
シャフトも硬いのでヘッドも軽く感じますが、
実際に グラファイトのウッド系に比べると
20g以上も軽めのヘッドがつけられています。
悪いことに アイアンは軟鉄全盛 の時代ですから
ヘッド自体も小ぶりです。
シャフトが硬く、クラブも短いほうのアイアンに軽い小ぶりなヘッド が付き
シャフトが柔らかく、クラブも長いほうのウッドに大型ヘッドが装着…
☞こんな組み合わせ うまく行く筈がない…というか
うまく行く可能性はとても低い組み合わせ…なのです。
故に…実はドライバーに苦しんでいる人の
本当の原因は それと組み合わせるアイアン にあるかもしれない…のです。
登録:
投稿 (Atom)








